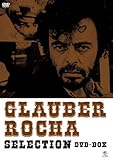グラウベル・ローシャ『狂乱の大地』『アントニオ・ダス・モルテス』
かつて作られた映画の中で、最も偉大な「騒乱」の映画がある。騒乱はもはや意識化から生起するのではなく、すべてを、民衆とその支配者たち、そしてカメラそのものを失神状態にし、すべてを逸脱させ、様々な暴力を交通させると同時に、私的な事柄を政治的なものの中に滑り込ませ、政治的な事柄を私的なものの中に滑り込ませる…神話の批判が特別な様相を呈す…古代の神話をまったく現代的な社会における衝動の状態に、飢え、渇き、性欲、力能、死、崇拝に結びつけること…数々の不可能性の上に成立する映画…カフカの耐え難いものの上に…ローシャの批判=神話の背後に生きられた一つの現在=耐え難いこと、生き難いこと、この社会において今生きることの不可能性のようなものを浮上させる。ついで、生き難いことから、沈黙させることのできない言語行為を、仮構作用の行為をもぎとること=神話への回帰ではなく、悲惨を異様な肯定性にまで高めることのできる集団的な言表の生産であって、一つの民衆を作り出すこと。 ドゥルーズ『シネマ2』p302~308より抜粋
砂丘で銃を天に向け、身体をねじ曲げる詩人。仲間を捜して奔走するが、政治の采配に振り回され、ジャズで踊り狂い、堕落し、女たちに接吻を浴びせる。
大衆が集い、1人の男に話す機会が与えられるが、「餓えている」という言葉を発したことにより、過激派扱いされ、袋叩きにあう。
民衆は大統領、政府に対して不平を言う。食料の確保とまともな労働を約束したはずなのに、汚職ばかりで自分の金と権力のことしか興味がない、と。詩人は相手に見切りをつけ、次の相手へと向うが、どいつもこいつも同じ結果に終わり、犬死にする。広大かつ空虚な大統領や知事の家は砂漠と荒野に呼応し、みなが疲れ果てた顔を見せる。詩人の女は常に詩人の男を支えようとするが、男は詩にも言葉にも絶望している。彼の問題は民衆を劣悪な環境から救い、まともな大地を街を甦らせることだが、民衆はしゃべることができず、しゃべったとしてもすぐに潰される。問題は末広がりになり、テレビや権力との闘いへ移行し、男は思考できなくなる。
詩人の男の表情は現在では明るくなることがない。常に皺を寄せ、大きく腕を振り回し、大声で叫ぶ。踊っていてもやけくそで、接吻すらもやけくそ。しかし、彼にできることはない。支持者を擁立し、教えても、うまくいかない。どうしようもない恋愛にかまけている。
大勢の民衆が踊り、喚き、テレビマンがカメラを構え、音楽が鳴り響くところで、詩人の女は男に「なぜあなたがここにいる必要があるのか」と問う。彼はその目で状況を見たかったのだろうが、女が言うように彼がそこにいる必要はなかった。
民衆は時折現れ、無駄な言葉を吐き散らし、喚くばかりで映画の中心には政府がある。そしてその中心は見えないところでいつのまにか動いている。
『アントニオ・ダス・モルテス』では民衆は1人の聖人の宗教によって楽しげに歌って踊ってばかりいる。それを好まない村の主が殺し屋を呼び、その中心にいる男(聖人の手下?)を殺すように指示し、遂行される。アントニオはただ黙している。先生は語り、悪人の邪魔をする浮浪者のふりをしている。そうしてだんだんとアントニオは状況を把握し、民衆の隠れた望みである悪人の排除こそが任務だと知るが、それは遅れる。立ち尽くし、座ったときは顔すら動かさずにいたアントニオが走りだすのはそのときだが、遅れ、新たな使命を知る。
自分のした過ちと言えなくもない過ちはキリストのように木に磔にされた男を発見したときに突きつけられる。先生は男の武器をとり、アントニオと二人で闘う。その後ろでフォルクローレが物語を語りつづける。自分の殺した男の死体を前にした沈黙、そこから始まる軽妙なフォルクローレ、そのうえで走り、飛び跳ね、銃をうちまくる男たち。
大きな背中には数々の死体が覆い被さるだろうが、それを罪と思い悩む必要はなく、沈思黙考し、動き出すときに動き出すまで。銃撃戦はギャグでしかない。動き回れるアントニオと思考できる先生に敵はいない。